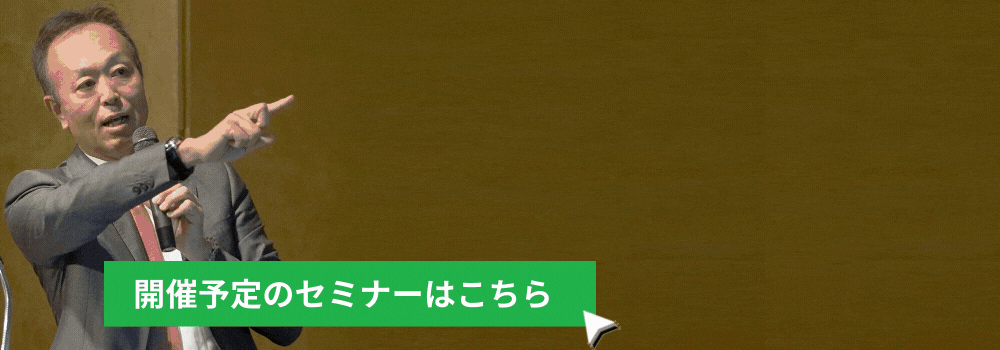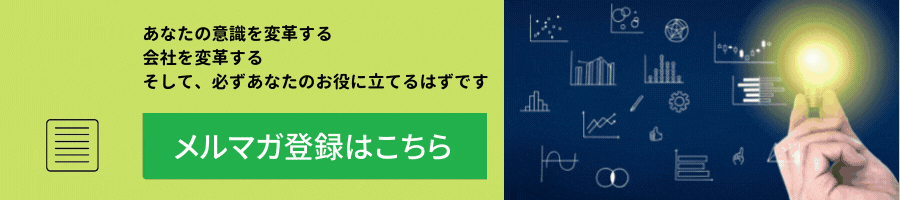ブログというと、短い文章が多いと思うのですが。
どうしても、できるだけ多くのことを伝えたくて、いつもいつも読むのがイヤになるくらい長文になってしまいます。
でも、私は、このブログが「コンサルティングそのものだ」と思って、書いています。
できるだけ第一線の現場の事例や情報、ノウハウ、手法を少しでも多くお伝えしたいと思っています。
一人でも会社経営に関わる人のお役に立てればと。
今年は、粉飾をしてしまっていた会社の再建や再生のお手伝いがたまたま多いようで、「粉飾決算をしていました。すいません。」ということを金融機関に説明にいくことが多くなっています。
経営者として、粉飾=水増しは絶対にダメなことはだれでも分かっているのですが、仕入先からの与信や金融機関からの借入のために、やむを得ずやってしまっているという方が、残念ながら多くいるように感じます。
しかし、経営者は自分で粉飾できるほどの会計知識を持っている人はそう多くはいないと思います。
ということは、関与している税理士の先生が、してはいけない指導をしてしまっていると言うことだと思います。
税理士の先生方にも、粉飾を指導するのではなく、粉飾から会社を立て直すためのアドバイスをしていただくことをお願いしたいと思います。
来年は、税理士の先生方を対象とした「会社の収益改善手法修得セミナー」を考えています。多分有料になると思いますが。
是非、税理士の先生方には会計や税務だけではなく、経営を学んでいただき、それを顧問先に指導をしていただきたいのです。
これで、救われる中小企業は数多くいると思うのです。
また、税理士の先生にとっては、他の税理士との差別化を図る強烈な付加価値になります。
ところで、粉飾決算から脱却したい経営者の心配事として。
「正直に、粉飾をしていましたと言って、本当に大丈夫なのか?」
「粉飾をしたら赤字になるのに、それで今まで通りの手形割引や手形貸付、当座貸越などの取引はできるのか?」
など、金融機関との取引がどうなるのかを心配される方が多くいます。
金融機関からすると、ある意味だまされたとも言えますので、金融機関への粉飾の言い方をひとつ間違えば、取引枠減少、あるいは取引停止と言ったこともあり得るかも分かりません。
このようなことにならないために、大事なことは、
- 「誰が」粉飾の事実を調べて金融機関に説明するのか
- どういう方法で、粉飾を説明するのか
ということです。
結論から言うと、社長一人ではダメです。
粉飾をしていた張本人ですから。
税理士はどうか?
「税理士の先生が金融機関に粉飾をしているんですよ、この会社は」とは言えません。
ご自分が関与しているんですから。
「客観的な第三者」がこの事実を、経営者と一緒に説明することが大事です。
「客観的な第三者」が言うことで、粉飾の事実を第三者的に説明することができます。
そのためには、財務デューデリジェンス(財務調査)を実施し、それを財務調査報告書といった書類にまとめ、それで粉飾の事実を明らかにします。
実際の説明の場では、重苦しい空気も流れることもあります。
金融機関の支店長から「これは重大な問題ですよ」と言われることもあります。
「これでは、うちも今後のことを考えないと」と言われることもあります。
でも、大丈夫です。
粉飾の事実だけで金融機関が取引を止めるのではなく、金融機関が取引を止めたり制限したりするのは、粉飾をしていたという事実ではなく、
- 粉飾に至った経緯と
- 今後どうなるのか
ということだからです。
粉飾に至った経緯は、財務調査報告書で客観的な第三者が明らかにすることが必要です。
大事なことなので、繰り返し言いますが、客観的な第三者が明らかにすることが、経営者にとっても金融機関にとっても極めて重要なことなのです。
これ以上のことは、このブログでは書けませんのでご容赦を。
あと、もう一つ大異な事があります。
粉飾を事実を明らかにすることで、赤字が明白になり、債務超過になる可能性が高くなります。
というか、私のクライアント先のケースでは、95%以上債務超過になります。
ということは、債務超過の解消年数とそのための対策を明確に記した「経営改善計画書」のようなモノが必要になるのです。
TKCがTVCMで言っているような「黒字経営のロードマップ、経営改善計画書」のようなレベルではなく、もっと具体的な収益改善策まで踏み込んだモノが必要です。
整理すると、「客観的な第三者が、財務調査報告書を作成し、経営者と一緒に、経営改善計画書を添えて、今後のことまで含めて説明する」と言うことです。
当然、真摯な態度で、謙虚に、過ちを認める姿勢が必要です。
このような準備をキチンとして説明すれば、金融機関からの支援がなくなるという事態は避けることができます。
それだけではなく、状況によっては今後の会社の改善に期待を寄せてくれる金融機関もあります。
支援をしてくれる金融機関も多くあります。
粉飾を続けるのか!
粉飾から脱却するのか!
決めるのは、経営者自身です。
将来の会社をどうするのか。
重要なターニングポイントだと思います。
大変な決断ですが、これが会社の命運を決めることになってしまうと思うのです。